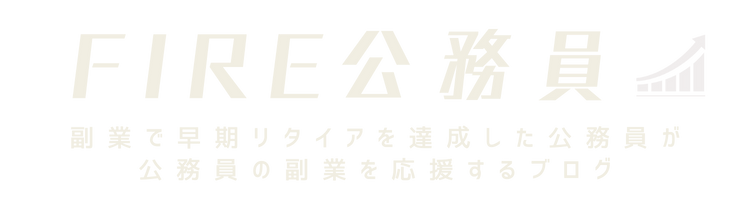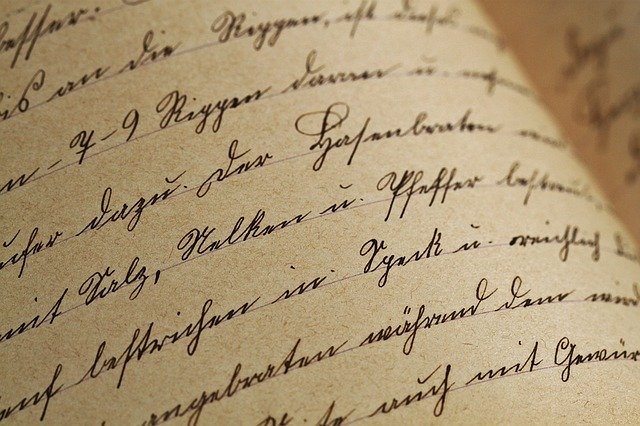公務員ですが小説を書きたいと思っています。可能でしょうか?

webライターといった執筆業によって原稿料をもらうことはできますか?

結論から言うと、出版も執筆業もできるよ!
もちろん原則、印税も原稿料をもらってもOKだよ!
公務員でありながら趣味で執筆活動を行う方は数多くいます。
それが高じて出版を行い印税収入を得るケースもあるかと思います。
また、新聞や雑誌から寄稿・連載を求められ、原稿料を受け取るケースもあるでしょう。
特に最近では、web小説など誰でも気軽に執筆活動を行うことができるようになりました。ちょっとバズっただけで出版社からオファーがくる世の中です。
そんなときに気になるのが、公務員でも印税収入や原稿料を受け取ることができるのかどうかですよね?
結論から言うと、印税収入や原稿料は原則、受け取りできます!
公務員が執筆業・出版をしても良い法的根拠

法令を根拠に確認していきます。まずは公務員の副業を規制している法令から見ていきましょう。
(私企業からの隔離)
第百三条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
② 前項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、これを適用しない。
③ 営利企業について、株式所有の関係その他の関係により、当該企業の経営に参加し得る地位にある職員に対し、人事院は、人事院規則の定めるところにより、株式所有の関係その他の関係について報告を徴することができる。
④ 人事院は、人事院規則の定めるところにより、前項の報告に基き、企業に対する関係の全部又は一部の存続が、その職員の職務遂行上適当でないと認めるときは、その旨を当該職員に通知することができる。
⑤ 前項の通知を受けた職員は、その通知の内容について不服があるときは、その通知を受領した日の翌日から起算して三月以内に、人事院に審査請求をすることができる。
⑥ 第九十条第三項並びに第九十一条第二項及び第三項の規定は前項の審査請求のあつた場合について、第九十二条の二の規定は第四項の通知の取消しの訴えについて、それぞれ準用する。
⑦ 第五項の審査請求をしなかつた職員及び人事院が同項の審査請求について調査した結果、通知の内容が正当であると裁決された職員は、人事院規則の定めるところにより、人事院規則の定める期間内に、その企業に対する関係の全部若しくは一部を絶つか、又はその官職を退かなければならない。
(他の事業又は事務の関与制限)
第百四条 職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。
出典:e-Gov国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000120#707)
(営利企業への従事等の制限)
第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)については、この限りでない。
2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。
出典:e-Gov地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)
(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#382)
要約すると、次の通り。
① 許可なく「営利企業の役員になる」のはダメ!(役員兼業の制限)
② 許可なく「自ら事業を営む」のはダメ!(自営兼業の制限)
③ 報酬を得てもいいが、兼業に当たる場合は許可が必要!(他の事業又は事務の関与制限)
※「職務専念義務」「信頼失墜行為の禁止」「守秘義務」は公務員としての大原則なので副業するときも守ること!
まず ①許可なく「営利企業の役員になる」のはダメ! ですが、執筆活動・出版活動によって営利企業の役員になるわけではないので問題ありません。
次に ②許可なく「自ら事業を営む」のはダメ! ですが、本を出版して印税を得るのは明らかに該当するといえます。したがって、印税収入を得るには許可が必要です。
過去には無許可で印税収入を得ていたということで処分された例もあります。
病気で休暇・休職中に無許可で小説を書き、印税を得ていたとして、神奈川県平塚市は20日、男性主事(28)を停職6カ月の懲戒処分とし、発表した。男性は同日、依願退職した。
朝日新聞デジタル(https://www.asahi.com/articles/ASPBN75R1PBNULOB032.html)
一方で、原稿料はどうなんでしょうか?
そこで最後の、 ③報酬を得てもいいが、兼業に当たる場合は許可が必要!について見ていきましょう。
争点は、原稿料が「報酬を得る兼業」にあたるかどうかになります。
この点については、ありがたいことに人事院のガイドラインで明確に要件が定められています。
次の2つを両方を満たす場合は許可が必要です。
以下の要件のいずれも満たす場合には、許可が必要です。
出典:「義務違反防止ハンドブックー服務規律の保持のためにー」(https://www.jinji.go.jp/ichiran/ichiran_fukumu_choukai.html)
① 労働の対価としての「報酬を得る」こと
② 「定期的⼜は継続的に従事する」こと
まず、原稿料は「報酬を得る」ことに該当する可能性が高いので①の要件は満たします。
一方で、単発の原稿料であれば「定期的⼜は継続的に従事する」ことには該当しないため、②の要件は満たしておりません。
したがって、兼業許可の必要はありません。
これを裏付ける人事院の照会例が次の通りです。
【照会例 12】
Q. 単発的に講演を依頼され講演料を得た場合や、研究成果等を雑誌等に単発的に発表し報酬を得た場合などは、第 104 条の兼業に該当しますか。A. 第 104 条における「事業に従事し、若しくは事務を⾏う」場合とは、「国家公務員としての職務以外の事業⼜は事務に、継続的⼜は定期的に従事する場合」を⾔いますので、上記のような単発的に従事する場合は、第 104 条の兼業に該当しません。
出典:「義務違反防止ハンドブックー服務規律の保持のためにー」(https://www.jinji.go.jp/ichiran/ichiran_fukumu_choukai.html)、太字は当サイトによる
なお、国家公務員倫理法・国家公務員倫理規程との関係では、当該依頼元が利害関係者であるときには、あらかじめ倫理監督官の承認が必要です。また、本省課⻑補佐級以上の職員については、講演料や原稿料等の報酬が 5,000 円を超える場合、原則として贈与等報告書を提出する必要があります。
これによると、単発的の原稿料を得た場合等は、兼業・副業には該当しないと明確に回答されています。
したがって、単発かつ社会通念上妥当な報酬であれば兼業にはあたらないので許可なく可能ということです。

地方公務員も、よほどのことが無い限り同じ基準だよ!
公務員法の副業・兼業に当たるケースは許可が必要
一方、「定期的⼜は継続的に従事する」場合は副業・兼業にあたります。つまり、許可が必要です。
例えば、雑誌の連載を受け持ったり、ウェブライターとして定期的に記事を提供し、その都度報酬を得ている場合は兼業にあたります。したがって許可申請が必要になります。
そうなったときに気になるのが「許可基準」ですよね。
実は、許可基準は内閣官房からの通知により、以下の通り明確化されました。
参考にして作成:閣人人第225号「職員の兼業の許可について」に定める許可基準に関する事項について(通知)(https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/jinji_e.html)

地方公務員も、よほどのことが無い限り同じ基準だよ!
実際に大阪府の事例でも、反復・継続的に報酬を得る場合は許可が必要だと解されています。
3.印税の取扱いについて
出典:大阪府HP 相談室 営利企業等の従事制限について(http://www.pref.osaka.lg.jp/shichoson/jichi/2705sodan.html)、太字は当サイトによる
「(中略)また、地公法第38条の「事業若しくは事務に従事すること」とは、職員が職務以外の事業又は事務に継続的又は定期的に従事することと解されるところである。
したがって、雑誌に原稿を寄稿し、それをもととした出版を反復・継続的に行う場合は、報酬を得て事業又は事務に従事することに該当し、任命権者から許可を受ける必要がある。」(『地方公務員月報 平成7年11月号』自治省公務員課編 24頁から25頁)とされています。
とはいえ、表現活動としての意味合いが強いので、よほどのことがない限り承認される確率は高いので安心してください!
- 単発かつ社会通念上妥当な報酬であれば副業にはあたらないので許可なく可能
- 「定期的⼜は継続的に従事する」場合には許可が必要で、許可基準が明確に定められている
公務員が執筆・出版する方法

公務員でも執筆・出版が可能ならば、ぜひともやってみたいと思うかもしれません。
執筆・出版には大きく分けて2パターンあります。
自ら作品を発表する
小説家などはこのパターンが多いですね。
実際に、立松和平 氏(元宇都宮市役所)、三崎亜記 氏(元福岡市役所)等々、公務員を続けながら作品を発表してきた作家はけっこういらっしゃいます。
2022年は、元自衛官で現役公務員の砂川文次氏が芥川賞を受賞しました!
今後も公務員と執筆活動を並行して進めるとのことです。
安定した公務員収入と、変動はあるが当たれば大きい執筆によるダブルインカムという、なんとも羨ましい状態です!
また、ややハードルが高いですが、自費出版や出版社への持ち込みといった方法もあります。

公務員の友人は文学賞に毎回作品を応募していたよ!
また最近ではweb小説が盛んです。有名になれば書籍化だけではなく、漫画化、アニメ化まで至るケースもたくさんあります。
これも元同僚の話ですが、趣味でweb小説を連載している方がいました。
それなりの人気があったので、もし書籍化依頼が来たら公務員を辞めて専業小説家になるつもりだそうです。
その余裕があってか、精神的にタフでしたし、仕事もめちゃくちゃできました笑

これこそ、本業公務員とは別の柱をもつ新しい公務員の生き方だね!
雑誌や出版社、webサイトからオファーを受ける
多くの場合、こちらのケースの方が一般的かもしれません。
例えば本業(公務)の関係から、公務員の業界誌からのオファーが来るケースはよく耳にします。
公務員でありながら、公務員試験受験ジャーナル(連載)や月刊ガバナンスなどに寄稿して原稿料を頂いている公務員もいます。
また、最近では地域活性化が盛んなので、ICT関連や都市計画で先進的な取り組みをしている自治体職員に依頼がくることもあります。
そのほかには、大学時代の研究について寄稿の依頼がくることがあります。
本業(公務)とは関係ない、あなた自身の専門知識を発表する機会であれば、継続的に報酬を得る場合でも、ほぼ承認されるでしょう。

研究関連はとくに承認が下りやすいよ!
さらに最近では、ブログやSNSで有名になると企業や団体から出版のオファーがすぐに来ることがあります。
ご存知の通り、ブロガーやYouTuber、インスタグラマーなど知名度のある個人がベストセラーを盛り上げています。
たとえばアウトドアに特化した趣味ブログが人気になると、アウトドア雑誌の出版社から続々とオファーがきます。
また、ブログやTwitterでマンガを連載しバズると、すぐに書籍化のオファーがくることもあります。
実際に、都立高校の教員がTwitterで連載していた育児漫画に対して、大手出版社からオファーがきたという事例もあります。
自身の育児経験をツイッターに投稿したエッセー漫画が人気を集め、出版社から書籍化を打診されていた。
出典:朝日新聞DIGITAL(https://www.asahi.com/articles/ASP5Z4FL2P5XUTIL01Q.html)
ただ、この事例では特段の理由が無いにもかかわらず教育委員会からの許可が下りなかったため、教員は都を相手取って取り消しを求める訴えを起こしています!

今後の裁判の動向に注目だね!
以上のように現代では出版のハードルがとても低くなっており、誰でも執筆活動で利益をあげるベースができあがっています。
公務員にも表現の自由は認められているため、完全に本業とは関係がなく、大原則(職務専念義務・信頼失墜行為の禁止・守秘義務)を守ればよほどの事情がない限り認められるはずです。
公務員がオファーをもらって執筆・出版をする流れ
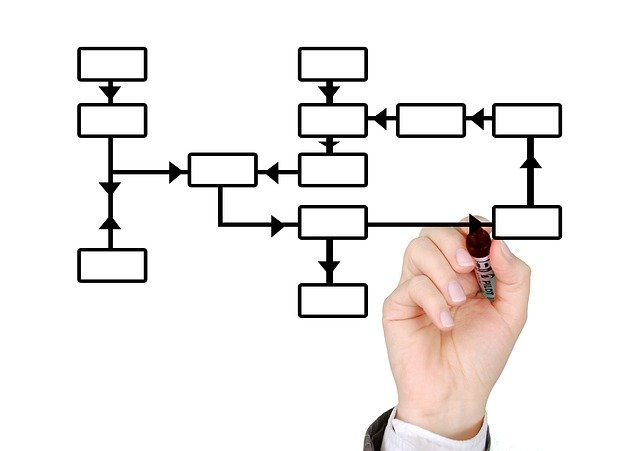
自ら作品を発表するよりも、雑誌の寄稿や出版のオファーをもらって原稿料をいただくケースの方が多いと思います。
そこで、もしオファーを受けた場合どうすればいいのか、流れを解説していきます。公務関連の単発オファーという想定で解説します。
完全にあなたの趣味や研究関連の場合はここまで綿密にやる必要はないでしょう。
①オファーを受ける
先方からあなたに寄稿や出版のオファーが来ます。
「○○というテーマで寄稿して頂きたいのですが、可能でしょうか?」
といった具合です。
内容やいただくお金について、必ず書面(メール等)でもらってください。

不要なトラブルを防ぐためだよ!
②上長に事前相談する
オファーの内容、頂く予定のお金(原稿料など)について説明します。場合によっては先ほどの書面の提出を求められます。
・先方と利害関係が無いこと
・大原則(職務専念義務・信頼失墜行為の禁止・守秘義務)に抵触しないこと
以上を示します。
単発なので必要ないはずですが、もし兼業許可申請が必要だと言われたら行いましょう。余程の理由がない限り承認されるでしょう
③オファー承諾の返答をする
オファーをくれた先方に承諾の旨を伝えましょう。
もし依頼文をもらう場合は、あなた個人宛の依頼文にしてください。
あくまで本業ではなく、私的活動によるものだと明確にする必要があるからです。
④人事に申請する
役所によって判断が分かれるところですが、人事に許可申請を出す場合もあります。
といっても上長の承認済なので書面に落とすだけです。期間に余裕をもって行って下さい。
⑤オファーを実行する
いよいよ執筆です。次のオファーに繋がる可能性があるので、全力で応えましょう!
⑥報酬を受けとる
報酬を受けとります。証明書は必ずもらいましょう。
また、いただいたお金が事前に聞いていたよりも増減があった場合は、念のため事後に上長に報告しましょう。
まとめ:公務員の執筆・出版活動はルールさえ守ればOK!
文章力に長けている公務員にとって、執筆・出版はとても向いている副業だと思います。
とくに現役公務員の砂川文次氏が芥川賞を受賞したこともあり、公務員作家の正当性、話題性は一気に向上しました!
堂々とできる数少ない副業なので、チャレンジしてみるのもいいかもしれません。
その他、公務員でもできる副業はたくさんありますので、こちらの記事で紹介しています!